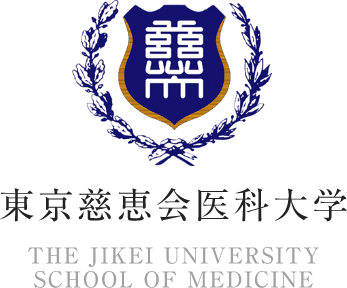自然科学教室
生物学研究室

教授
橘木 修志
研究室概要
1960年4月、進学課程の開講に合わせて設置された生物学教室が本研究室の起源です。その後、生物学教室は、1998年に解剖学講座第1・生物学研究室へと改組されましたが、2002年、自然科学教室を構成する生物学研究室へと再改組され、今日に至ります。2024年現在、設立から65年目となります。
[email protected]
物理学研究室
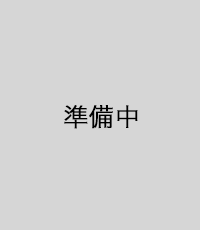
教授
植田 毅
研究室概要
神羅万象、この世の物体やエネルギーの状態の変化は物理法則に従っており、ヒトも例外ではありません。生命体はタンパク質、脂質、塩基などから構成され、生命現象は生体分子の複雑な物理・化学現象で、物理学の基本法則に従っています。医療機器は物理現象を応用し、医療で行われる処置、手技も科学的根拠のもとに行われています。物理学研究室は、医学の道を歩む基盤づくりとして、「生命を科学的に学ぶ」一翼を担っています。
化学研究室

教授
小宮 成義
研究室概要
本研究室は、進学課程が開設された1960年から化学研究室として初年次学生に基礎科学としての化学を有機化学や物理化学を中心に教育してまいりました。1998年からの生化学講座第1・化学研究室の時期を経て2002年から自然科学教室・化学研究室として現在に至っております。
人間科学教室
社会科学研究室

教授
麻生 多聞
研究室概要
多様な価値観が共存する社会のあり様を前提とし、医療人の専門的アイデンティティは、広く市民の生活の論理や、医療環境を取り巻く社会の論理に立脚するものである必要がある。医学教育における社会科学の位置づけをめぐり、臨床実践と高度な関わりを帯びる専門性の一部としてこれを捉えるべきことが指摘されている。そのような社会科学的知と将来の医療を担う慈恵の学生を架橋すること、これが社会科学研究室の使命である。
[email protected]
人文科学研究室

教授
三崎 和志
研究室概要
国領校での人文科学教育を統括しています。医療従事者に求められる人文科学の素養とは何か、ということを考えながら、人文科学の教育にあたっています。
[email protected]
日本語教育研究室

教授
野呂 幾久子
研究室概要
人間科学教室は、医学科国領校で主にコース総合教育を担当するスタッフが所属する教室として、2002年4月に、法学・心理学・日本語教育・数学の4研究室を統括する教室として設置された。現在は、社会科学・人文科学・日本語教育・数学の4研究室を統括している。
数学研究室
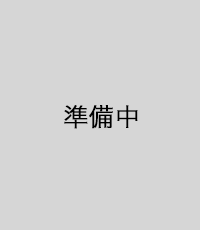
教授
横井 勝弥
研究室概要
本学では、教科「数学」の教育を大正10年(1921)の旧制予科時代から行っています。数学教室(研究室)としての歴史は、昭和35年(1960)の進学課程設置時に、木村教雄教授が初代教授として着任されたときに始まりました。その後、衣笠泰生教授、鈴木皖之教授と続き、現在は、横井勝弥教授を中心として医学科・看護学科における数学・数理統計学の教育と研究を進めています。
外国語教室
英語研究室

教授
ハウク アラン
研究室概要
昭和54年「進学課程」2年制の当時、英語教室とドイツ語教室がありましたが、平成3年「医学科国領校」1年制となり、同8年には外国教育がコース総合教育のユニットとなりました。平成14年に再改変が行われ、英語研究室、ドイツ語研究室となりました。平成15年より2〜5年生までの英語課目は医療英語の専門教員が担当し、医学科1年生、看護科1〜2年生の英語は、英語教育専門の教員が担当しています。
初修外国語研究室

教授
鈴木 克己
研究室概要
外国語教室は、昭和35年、進学過程発足時に設立された語学教室という名称でその歩みが始まります。昭和54年に語学教室はドイツ語教室と英語教室に分かれました。平成14年の組織改変で、ドイツ語教室、英語教室がそれぞれドイツ語研究室、英語研究室となり、この2研究室をまとめて外国語教室と呼ぶようになりました。平成20年、ドイツ語研究室が、初修外国語研究室と改名され現在に至ります。